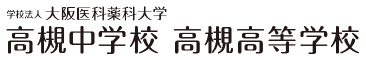2月6日(木)、大阪公立大学 理学研究科 教授の名波哲先生をお招きし、「植物のメスとオスの話 その多様で複雑な性」と題した大学0年生講座を開催しました。
講演では、植物にはさまざまな性があり、その性もいくつかの動物のように性転換することを聞き、生徒たちも驚いていました。また、野生でのクローン植物の規模の大きさやその意義について知識を深めていました。

受講生徒の感想
- 植物の性は動物と全く違って多様で驚きました。今まで、クローンの動植物は同じ病気に弱いのでそれに感染すると全滅すると思っていたので、その事例がバナナだけであることを初めて知りました。(中1)
- 植物が両性花、雄花、雌花という種類をもっていることは知っていても、それを混雑させて咲かせているということを初めて知り驚きました。また、性転換やクローンの言葉自体は知っていても、その意味やその実態は初めて知りました。性転換する植物や動物としないもの、多様な遺伝子を持つ植物やもたないものの比率や、どちらがどのような環境で競争力が強いのか調べたくなりました。(中2)
- 性転換のことは何となく聞いたことがあったけれど、一定の条件ですべて雌になったりすると知り、驚きました。クローンだと環境に適応できなくてすぐに絶滅するものだと思っていたので、意外に長く生き残れる植物もいるとわかりました。植物にはまだナゾが多いそうなので、私も知識を深め親しみたいと思いました。(中2)
- 教科書を読んで遺伝的多様性が低い生物は絶滅しやすいのかなと思っていたけど、バナナの例だけで、多くのクローンは広い範囲で今も生きているというのが意外でした。羊のクローンのドリーは学校の授業で最近知ったばかりだったので登場していてうれしかったです。(中3)
- 植物には多様な性があって、それぞれに長所や短所があるのがおもしろかった。今、ちょうど授業で陽樹やギャップなどについて学んでいたので、ウリハダカエデの体調が悪くなると雌になる理由の仮説が感動した。(高1)
- 自分の好きなテンナンショウ属の中のマイヅルテンナンショウが両性花と雄花をつける理由がわかって助かりました。(高2)